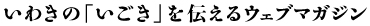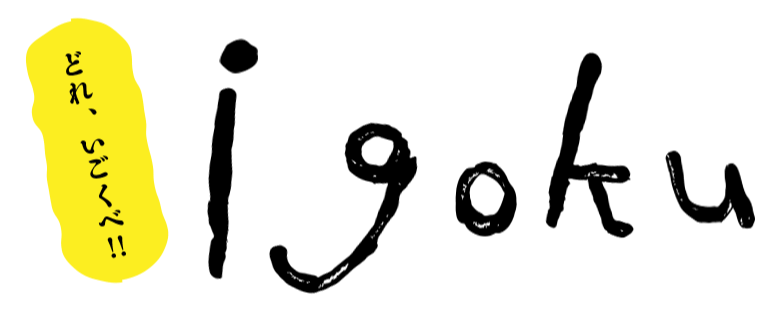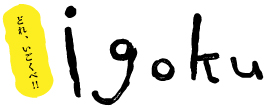2025年9月27日、いわきアリオス・セキショウ中劇場を会場に、生と死の祭典「いごくミーティング2025」が開催された。2018年2月に最初の「いごくフェス」が開催されてから7年半。これまでのフェスでは「極楽浄土」や「極彩色」といった尖った言葉がテーマに掲げられていたが、今年のテーマは「en」。意外なほど “地味な” テーマとなったが、当日はどのような時間が流れていたのか。そして、これまでのフェスとなにが違っていたのか。いごく編集部の小松理虔がレポートする。

いごくミーティングは、いわき市地域包括ケア推進課が主催する「生と死の祭典」。医療や福祉、介護、まちづくりに奔走してきた人たちを表彰するとともに、さまざまなステージプログラムを通じて、生老病死、つまり人生について、参加者みんなでおもしろおかしく思考を深めて、これからの人生に活かそうじゃないかというイベントだ。
本題に入る前に、いごくフェスの歴史を振り返っておこう。第1回いごくフェスが開催されたのは2018年2月。老いや死をテーマにしたステージや入棺体験で話題をつくると、同年9月の第2回からは「屋外&屋内の2段構え」に進化。食あり演芸あり歌あり踊りありのエンターテイメント空間に多くの人たちが集った。
2020年に開催された第4回はコロナ禍。「感染拡大防止」が叫ばれるなか「シン・密」をテーマにオンラインで笑いと思考を届け、爪痕を残した。しかしその後、感染は緩やかになったものの、医療や福祉の領域では感染拡大防止が叫ばれ、大人数が集まるイベントの開催は難しくなってしまった。そこで、2023年は規模を縮小し、地域包括ケア推進課の職員が中心となって「ミーティング」形式、小規模での開催となった。
最初のフェスから7年半となる今回。名称は「ミーティング」だが、内容的には原点回帰と言えるだろう。いごく編集部のメンバーが企画段階から関わることになり、プログラムも、ゲストのメンツも、かつてのような「いごくらしさ」を感じる構成へと戻ったかたちだ。
みんなで笑い、みんなで祝う、宴の力
オープニングアクトは、いわき吹奏楽団。過去のフェスでもオープニングを務めてきた彼らだが、久しぶりの「igokuステージ」とあってテンションが高い! 1曲目は東京スカパラダイスオーケストラの『Paradise Has No Border』、2曲目には西城秀樹の『ヤングマン』。どちらもノリノリの曲だ。指揮者が観客に合図して、みんなでぐいっと手を挙げ、体を動かして一体感をつくっていく。しかもその動きはどことなく「シルバーリハビリ体操」っぽい。優しく、そして激しく会場の体温を上げ、風のように去っていく姿が最高だった。

序盤からテンションマックスのパフォーマンス

みんなで楽しくY.M.C.A!!
いわ吹の演奏のあとは、igoku表彰式。この表彰式は、いわきの医療や福祉の領域での「いごき」を表彰するものだ。今回は、シルバーリハビリ体操の考案者である大田仁史先生、そして、いわきの地域医療に尽力されてきた木村医院院長の木村守和先生のお二人が表彰された。
現在、いわき市の各地で開催され、多くの市民のへルスケアを支えているシルバーリハビリ体操をつくった「張本人」が大田先生である。シルリハ体操は、ベッドに横たわることしかできなかった患者が、体を起こして座れる⇨立てる⇨そして自分で歩けるようになるところまで、プロのリハビリ専門職が担うものを、日常的かつ自分たちでできるよう、わかりやすい体操にしたものである。

95歳の「教え子」から表彰される大田先生!
それを「発明」しただけでも大きな功績だが、大田先生の功績はそれだけではない。シルリハ体操を地域に普及させるには体操の指導者が欠かせない。そこで大田先生は、指導士の養成まで自ら先頭に立って推進した。いわき市のシルバーリハビリ体操指導士は今や877人を数える。今やいわき市は、日本でもっともシルリハに臨む自治体になりつつある。大田先生なくしていわきのシルリハなし、なのである。
受賞後の挨拶で大田先生はいう。健康な人たちだけではなく、弱くなっていく人も、悪くなっていく人も一緒にできる体操でなければいけないと。ひとつ象徴的なシーンがあった。いわきでシルリハ体操に日々勤しむ、なんと95歳!の女性が、表彰式のプレゼンターを務めたのだ。95歳なのに足取りも軽やかで、記念のトロフィーを軽やかに大田先生に手渡していらっしゃった。この軽やかな動きは、まさにシルリハの賜物だろう。

大田先生は、レディの手を引いて颯爽と退場

いわきのigokuなシンボル、シルリハ体操
もうひとつ、思い出すシーンがある。退場のとき、大田先生が女性の手を取り、優しく手を引いて退場していったのだ。人生の先輩たちを優しくエスコートする大田先生の姿には、シルバーリハビリ体操がここまで普及した理由、そして、「最期の瞬間まで自分らしく生きる人を支えたい」という大田先生の死生観、リハビリ観が凝縮しているようだった。表彰のあとは、もちろんみんなでシルリハ体操をやる。それもよかった。

igoku表彰を受けた木村守和先生
次の表彰者は、いわきの地域医療に尽力してきたレジェンド、木村守和先生。四倉にある木村医院で医師・院長として働きながら、いわき市医師会の会長も務めるなど、医療と福祉、介護の地域連携を進めるために奔走してきた。だが、これからのさらなる活躍が期待されていた矢先、全身の筋肉が萎縮する難病の「ALS」に罹患。現在は、病気と向き合いながら、自分の声を学習させたAI音声を使い、地域医療の充実のための講演活動などを続けている。まさに不屈の医師。
木村先生はAI音声を駆使して次のように挨拶した。だれもが健康で長生きしたい。けれど、病気や障害は、いつ誰かに降りかかるかわからない。だからこそ、高齢で虚弱になっても、障がいを持っても、住みなれた地域で安心して暮らせる地域をつくっていきたい。医師と患者で、立場は正反対になったけれど、在宅医療と地域包括に取り組んできて本当に良かった。これからも、この障がいを持った人生を生きていきたい。

守和先生は、AIの音声を使って挨拶した
木村先生が時折笑顔を見せているからか、その言葉に悲壮感は感じない。そればかりか、木村先生は幾度も周囲に感謝の気持ちを伝えていた。だれかに支えられながら、そして自分もどこかでだれかを支えながら、「このわたし」を最期まで生きていく。木村先生から溢れる情熱、そして背後にある周囲への感謝の気持ちが見え、心を打たれた観客は少なくなかったのではないだろうか。
ふと、過去の受賞者のことが思い出された。ケーシー高峰さん、菓匠梅月の片寄清次さん、さらには、みろく沢炭鉱資料館の渡辺為雄館長・・・。みんな逝ってしまった。人は死ぬ。だからこそ人生は尊く、最後の瞬間まで自分の人生を楽しみたいとだれもが願う。そして、人は死んでも、だれかの心の中で生きていくことができる。igokuを通じて出会ったあの人も、あの人も、私たちの心で生き続け、光を放っている。そんなことも、表彰式の歴史は伝えてくれている。

会場の皆さん、にこやかな表情を浮かべていらっしゃいました
会場には、どこかほんわかとした熱気が生まれていた。みんなで体を動かし、みんなで笑い、みんなで、だれかの健闘を讃える。いわば「宴」の力。これは後半のステージでも言えることだけれど、今回のいごくフェスでひときわ感じたことだ。たくさんの人たちで、なにかひとつのことに向き合ってみる。すると、なんだかいい感じの一体感が感じられてくる。「グルーヴ」というやつだ。
お葬式が簡略化され、故人の業績や想いに触れる機会が年々小さくなっているなかで、何百人という人たちのグルーヴでもって、目の前の人のいごきをねぎらい、拍手を送り、「いわきでいごく(そして死んでいく)」ことについて思いを馳せる機会なんて、そうそう作れるものではないな、と思った。もしかしたらこの表彰式は、いわきでいごき続けてきた人たちの、だいぶ気の早い「生前葬」だと言えなくもない。
もちろん、大田先生も木村先生も現役バリバリだけれど、いつかはお迎えが来る。その前に、その志を、情熱を、レジェンドたちが現役でいるうちに受け取り、いごきのバトンを受け継いでいく。この表彰式は、そういう儀式の時間なのだと思うと、余計に、過去にこの表彰式に参加されたみなさんの顔が目の前に浮かんできた。

ロバ隊長を授与されたいわきFCの皆さん
続いて行われたのは、認知症への正しい理解と啓発活動を率先して行ってきた団体を表彰する「ロバ隊長授与式」だ。ロバ隊長というのは、認知症サポーターのマスコットキャラクターであり、急がずに、一歩一歩「認知症になっても安心して暮らせるまちづくり」を進もうというメッセージが込められている。
今回は、いわきFCを運営する株式会社いわきスポーツクラブ、さらには株式会社マルト、いわき市立大浦小学校にも、ロバ隊長のぬいぐるみが手渡された。当事者と支援者ばかりではなく、その活動を外側に拡張、延長していく。そうした取り組みは、これからの時代、さらに必要とされていくことだろう。

みんな「いごき」を讃えあうこと。それがフェスの醍醐味
その人の立場に立ってみる、演の力
いごくミーティング後半は、演劇を中心とした「いごくステージ」。まさに、今回のテーマ「en」を体現する時間になった。出演する団体は、劇団ごきげんよう、ふたば未来学園高校演劇部、そしてigokuフェスに毎回出演してくれているロクディムの3組。それぞれ、この日のためにテーマや演目を設定し、稽古を重ねてきた。
地元いわきの劇団ごきげんようは、医療や福祉の領域で家族トラブルの象徴として語られる「カリフォルニアから来た娘症候群」を作品化した。「カリフォルニアから来た娘症候群」というのは、親の死期が迫ったときに、「遠」方から帰省した家族(多くの場合子ども)が、慎重に組み立ててきた本人と家族の合意をひっくり返し、無理な延命治療を求めたり、ケアの方針に異論を唱えてしまったりすることを表す言葉である。

俳優たちの迫真の演技。会場のみんなが「延命」について思いを馳せた

ベッドの脇で、和解の時を迎える姉妹たち
今回の作品でも、母親と長女は父親の「延」命治療は行わないという合意をとっていた。だが、いよいよ死期が迫った父を前に、突如帰省してきた次女が「延命しないなんてひどい!」と家族に怒りをぶつける。母親や長女にとってみれば、次女は、日々の介護や介助を手伝ってきたわけでも、父との合意の場にいたわけでもない。だが、そんな次女も大切な家族の一員であり、母親だって長女だって、当然、父親には1日でも長く生きてもらいたいと思っている。だからこそ難しいのだ。
死期が迫り、病床で一言も発することのない父を前に、家族の葛藤が描かれる。その演技はあまりにも真に迫っていた。いわきの役者が演じていて、地元の言葉で語られるから余計にそう感じるのだろう。役者は演じている。現実ではないのはわかっている。けれど、舞台上で繰り広げられているものが、現実のように思えてしまう。それが「演」の力。
会場から、時折鼻を啜るような音が聞こえてきた。おそらく多くの来場客が、「延」命とはどうあるべきか、家族と一緒に考えておくことがいかに大切かを痛感したことだろう。何百枚もプリントを配布してきても伝わらないことが、たった15分の劇で届いてしまう。改めて演劇というもの、舞台というもののパワーを痛感させられる時間だった。

高校生たちの熱演を通じて、「認知症」を考える時間
2組目。ふたば未来学園高校の作品は、昭和村に住む、元女性教師のおばあちゃんの人生の終盤戦を舞台にしたものだった。古い家に一人暮らし。なんでも一人でやっていたおばあちゃんだったが、耳が遠くなり、次第に、耳の奥で反響する音を「だれかが家の2階で生活しているんじゃないか」と考えるようになる。その不安が大きくなり、鍋にしゃもじを打ち付けてカンカンと鳴らし、家の中の「住人」を追い出そうとしたこともあった。
周囲の理解や助けもあり、おばあちゃんはめでたく100歳を迎えた。村民のほとんどが教員時代の教え子だ。お祝いしてくれた町長も、職員も教え子。認知症でも昔のことならはっきりと覚えているから、教え子との昔話はとても明晰。だから、久しぶりに会う人は、先生が認知症だなんて気づかないかもしれない。そんな「老いのリアリティ」も存分に混ぜ込みながら、おばあちゃんが天寿を全うするまで、生徒たちの演技は続けられる。

主人公は実在の女性であったことが写真とともに伝えられる
高校生が演じるのは100歳のばあちゃんだから、リアリティがあるわけではない。「演じている」ことがはっきりと理解できる。けれど、おばあちゃんは実在の人物であり、エピソードはどれも本当のことなのだ(実際の写真が舞台上で大写しにされることからそれがわかる)。だからこそ、生徒たちが言わんとしていること、ばあちゃんの生き様が伝わってくる。観客それぞれに、認知症について、親の介護について、自分の思い出や考えとすり合わせながら鑑賞することができたのではないだろうか。

ロクディム登場。igokuフェスに欠かせない存在
最後の舞台は、いごくお馴染み即興演劇集団「ロクディム」。事前に会場から収集したアンケートをもとに即興で演劇を繰り広げていくスタイルだ。俳優たちが即興で繰り広げていく数分間の短い劇中に、紙に書かれたセリフが挿入される。上手くハマった時には会場から「おおおお」っという声と共に拍手が巻き起こるし、そうじゃない場合も、俳優たちがそれを引き取り、なんとか劇を成立させていく。
今回は、即興演劇の「スタートの設定」も、観客からのリクエストから決められた。観客席に座ったある男性が「麻雀」をリクエストすると、壇上の5人の俳優たちは、久しぶりに仲間たちと麻雀をしに集まった男性たちに扮し、劇を繰り広げていく。主人公役のお父さんは、なんとかして「国士無双」を決めたい。のだが、その雀卓で、丁々発止のやり取りが続いていくのだ。

無造作に散らされた「セリフ」を拾いながら劇は即興で繰り広げられていく
ロクディムの俳優たちは、観客から寄せられた言葉も、俳優同士の即興の言葉も、すべてポジティブに拾い上げていく。そこで鍵を握るのは、どういう言葉を出すかではなく、出された言葉をどう拾うかだ。どんなにおかしな言葉も、あさっての方向からの言葉も、受け止め方次第で、ポジティブで味のあるものに変わっていく。ロクディムは、即興のやり取りを通じて、そのことを観客に伝えていっているのではないかと思えた。
福祉の現場にも、似たようなことが言えるかもしれない。利用者さんが、なにか空気を読まない発言をしたとする。でも、「そんなこと言うのはおかしい」とは言わずに、何気ないひとこととして静かに受け止める「フリをする」ことで、たいしたことじゃないよ、いつも通りだよ、なんとかなるよと伝えていく。それはきっと福祉の現場の日常にありふれたものだろう。その「演の力」が、ケアの時間を支えていると言えないだろうか。

雀荘を舞台に、「国士無双」の物語が展開されていく
エンタテイメントの力、エンパワメントの力
久しぶりのいごくミーティング。表彰式と演劇と、大きく分けて2つの展開しかないとてもシンプルで飾らない時間だったと思う。だからこそ、押し付けがましくなく、観客それぞれが思考の糸を手繰り寄せながら、老いや死、老後や家族、そして地元について考えたのではないだろうか。
今回改めて感じたのは、「宴」と「演」、ふたつの「en」の力である。それに加えて、もう二つほど「en」を加えたいなと思った。ひとつが「エンタテイメント」、そしてもうひとつが「エンパワメント」である。
エンタテイメントとは「娯楽」だ。心がグッと掴まれるような時間のなかで、時を忘れて笑顔になり、「あ~ぁ、楽しかったなぁ」という時間のなかに、ぽつりぽつりと問いが残されていく。それがいいのだ。まちづくりには、有識者が集まって意見を交わしたり、やる気のある住民が集まってワークショップをする時間も必要だけれど、そればっかりだと疲れてしまう。みんなで笑って体を動かし、楽しく盛り上がりながら、それぞれの距離で人生や社会に向き合っていく時間が、もっとあるといいなと思う。

俳優たちが繰り出す、enの力

非日常の空間で繰り広げられていくのは、わたしたちの日常
そして、そういう「あ~ぁ、楽しかったなぁ」という時間に、素敵な人たちが登場したり、そこはかとなく専門的な知恵や知識が入ることで、「よし、明日もがんばるか!」という力になるだけでなく、活動のヒントやアイディアになっていったりする。エンパワメントとは、目の前の人が本来もつ力を引き出すこと。上からこれをやれと言われるんじゃなく、内側にある力が目覚めていく感覚が、いごくミーティングからは感じられた。
辞書で調べてハッとした。英語の接頭語「en」は、「…の中に入れる」という意味をつけたり、「…にする」「…になる」という意味の動詞をつくる働きがある。ちなみに、エンタテイメントの「enter」とは、中に入った状態、「…の間」のことを指す。「tain」は「つかむ」という意味があり、「entertain」で「心の中に入ってつかむ」になる。

演者と関係者の大団円。igokuはやはり、igokuであった
演、宴、延、遠、援、円・・・漢字の「en」を想定したテーマを掲げていたけれど、終わってみれば、それらはどこかで、この「中に入れる」「…にする」という「en」とも響き合っていたように思う。いわば「enigoku」。人と人のつながりや地域の中に入り、時に演じて、時に縁を催してエンパワーし、遠くまで、そのつながりを延ばしていこうとすること。そして、そのメッセージを、エンタメの力を借りることで、伝えていくこと。
終わってみれば、いごくミーティング2025、どこまでも「いごく的」であったと思うし、その「いごくらしさ」は、すでに地域のなかで「いごいてきた人たち」によってつくられていることを、今年も思い知らされた。思い通りにいかない人生を、日々を、それでも少しずつ「円く」おさめていくために必要なもの。それが「en」なのかもしれない。
公開日:2025年11月06日