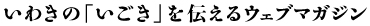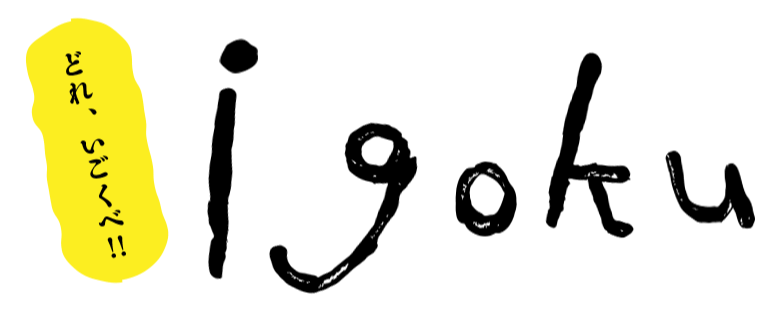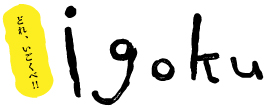2024年4月1日、いわき市民の生活の足を支えるバス会社「新常磐交通」が大幅なダイヤ改正を行った。かねてより深刻だったバス運転手の高齢化や担い手不足が原因であるのはもちろん、働き方改革関連法が変わり、バス運転手の労働時間規制が強化されたこともダイヤ改正に拍車をかけた。4月1日に発表されたニュースによると、利用者が少なかった14路線57系統の沿線が廃止され、平日は74便、土日祝日は139便が削減された。私が暮らす中之作でも、休日便の運行はすべてなくなった。
ダイヤ改正をうけ、SNSにはさまざまな意見が飛び交っていて、中には担い手や行政に対する不信感を表す意見もあった。私たちの暮らしは他者が担うサービスによって支えられているわけだが、他者の存在が見えにくくなり、サービスの「担い手」と「受け手」という関係が強化されるほど、暮らしの選択肢を失って、不利益をこうむるかもしれないという「受け手」としての思いが強くなるのかもしれない。
担い手不足はバス業界に限った話ではない。担い手不足を解消すべく、国をあげて少子化や人口減少への施策は打っているものの、依然として歯止めが効かない状況が続いている。今後、あたりまえにある(とされている)サービスが立ち行かなくなるケースはますます増えてくるだろう。あたりまえがなくなってしまった(失われようとしている)とき、受け手である私たちは現実をどのように受け止め、どのように行動すべきなのだろうか。
なんとも暗澹とする時代だが、こうした状況や閉塞感を打開するヒントとなる取り組みが、実は、このいわきでも実践されている。いわき市の最北端・川前町にある「特定非営利活動法人小さな拠点おおか」。そして、その「おおか」が行っている「自家用有償旅客運送・おおか号」の取り組みだ。
具体的な内容についてはのちほど詳しく紹介することとして、まずこの二つの事業の特徴をわかりやすく紹介してしまうと、それは、どちらの取り組みも「行政サービスに代替する新たな取り組みが民間主体で生まれている」という点である。過疎化が進んでいるとされる川前だが、二つの取り組みは、住民と行政、住民と民間団体・企業の協働の取り組みになっているのだ。なぜこのような取り組みが生まれ、市民の手で運営することができているのだろうか。その背景や協働のポイントを、小さな拠点おおかを運営するみなさんに伺った。
-サービスがなくなりつつある川前町
編集部が川前町に向かったのは、3月下旬。おおか号の出発式と、コミュニティカフェ・小さな拠点おおかのオープンイベントが行われるということで、門出のお祝いにと取材に伺った。igokuでおおかを取材するのは、実は今回で2回目。前回は、雪が降り積もる中でリノベーション前の拠点を見学し、NPO法人小さな拠点おおかの設立総会を取材した。その後SNSで変貌を遂げる様子はみていたものの、現場に足を運ぶのは約1年ぶりになる。
いわきの中心部から川前町までは車で1時間ほど。険しい山道をドライブしながら、うごきはじめた拠点を間近でみられることへの期待が高まっていく。町中に到着すると、「桶売中学校、ありがとう」の看板が目に留まった。

閉校が決まった、まち唯一の中学校
川前町は、桶売・小白井・川前の3つに分けられていて、それぞれの地区に小中学校があった(ちなみにおおかの名前も、「お」けうり・「お」じろい・「か」わまえそれぞれの頭文字からきている!)。以前は、子どもたちは当たり前のように地元にある学校に通い授業を受けていたが、2023年度、川前町にある全ての小中学校が閉校になった。「学校もなくなってしまうのか」。そう思った私は、「ありがとう」の看板を間近で見たくなり、車を停めた。
以前の記事でも紹介したが、川前町はいわき市でもっとも過疎化が進むまちで、高齢化率は50パーセントを超えている。小中学校だけでなく、もともと運営されていた診療所がなくなり、あたりまえにあるはずのサービスが受けられない状態が続く。こうしてデータや事実を並べてみると、やはりサービスが充実している都市部のほうが豊かに暮らせるのではないか、そんな考えが浮かんでくる。しかし、暮らしの豊かさは客観的なデータだけで決められるものではない。最期をどこで迎えたいか。どの地域で暮らしたいか。それを決める決定権は本人にあるからだ。
おおかという組織が立ちあがった背景には、川前で暮らす人たちが「最期まで住み慣れた川前で暮らす」ための基盤をつくるという目的があった。これからもこの地で暮らし続けていくためには、これまでサービスが担っていたものを住民同士で補い合う助け合いが必要になってくる。極端な言い方になるが、川前では、何かことが起きたら助からない可能性を考えなければならない。医療機関がなく、市内の中核病院に搬送するにも時間がかかるし、そもそも平時の医療サービスすら希望通りには受けられないからだ。
ならば、病気になる手前で積極的に介入し、病気にならないように、病気があったとしても重症化しないように、その人の暮らしを地域全体で支えていこう(いくしかない)。そんな「逆転の発想」が、組織づくりの根底にあったのではないだろうか。前回、NPO法人小さな拠点おおかの設立総会を取材した時の顔ぶれを思い出す。川前在住もしくは川前出身の民生委員、地域包括支援センターのスタッフ、福祉施設を運営する方など、まちや福祉に詳しいメンバーが多数出席していた。その顔ぶれに、川前で暮らし続けようとする地域の覚悟が見えた気がした。
-「コミュニティナース」が拡張するもの
川前と同じように「病気になる手前」の状態に着目した取り組みは全国各地で行われている。ちょっとそちらに寄り道しながら考えてみたい。まず参考にしたいのが「コミュニティナース」の考え方だ。
コミュニティナースは「人とつながり、まちを元気にする」行為やあり方、概念を指している。医療資格の有無で判断されるものではない。この定義は、日本のコミュニティナースの第一人者で、島根県出雲市を拠点にコミュニティナースを実践する株式会社CNC(Community Nurse Company)の代表・矢田明子さんが提唱するものだ。「コミュニティナーシング(地域看護)」という看護の実践からヒントを得たという。
ナースという名詞は入っているが、世間一般的にイメージされる看護とはちょっと違う。同社が具体的に行っているのは、まちなかにある活動拠点での交流や住居への訪問だ。コミュニティナースの実践者は、まず、地域に暮らす一人ひとりと顔の見える関係を築いていく。そして、そこで知り合った住民の力を借りながら、住民の「やってみたい」を形にしたり、お困りごとを解決したりするためのアイディアを考え、実装していくという。最終目標には、一連のプロセスの中で結果的に「助け合うコミュニティ」が育まれることが掲げられている。
こうした現場を支えているのが、矢田さんが提唱する「健康おせっかい」だ。支援なんて必要ないと思っている人も巻き込み、人と人とをくっつけ、人の間に人を介在させて関係をもたせてしまう、というものである。つなげるためには一歩踏み込む必要がある。おせっかいでもいいからグッと関係に踏み込んで、地域の人たちをコミュニティの網の目につなげてしまうのだ。
地域のプロジェクトで「つながりづくり」と聞くと、商店街の活性化とか、地域の担い手の育成とか、そういう文脈で耳にすることは多い。だが、多くの場合、「力を持つ人たちの人間関係」として表出されることが多いように感じる。A社長とB社長がつながってこんな取り組みが生まれたとか、地元にはこんなすごい人たちのネットワークがあるとか。強者のネットワークばかりが可視化されてしまう。
コミュニティナースは、いわば「弱さ」によってつながる。弱い地域で、少ない住民で、みんながさまざまな困難を抱えているからこそ「おせっかい」が必要なのではないだろうか。だれかのおせっかいを通じて「のりしろ」ができ、その「のりしろ」で人と人がくっつく。そうしてネットワークができることで、人がコミュニティからこぼれ落ちることを防ぐことができるようになり、病気や重症化を未然に防ぎ、自分らしく生きられる地域づくりにつながっていく…。私は、コミュニティナースをそんなふうに解釈している。
医療や福祉の専門的な資格がなくても、病院や施設でなくても、人の間に入り、人をつなぎ、まちに関わることならできる。既存の枠にとらわれない「コミュニティナース」の考え方は、おせっかいな人や誰かを気にかける人、そして「おおか」のみなさんのうごきそのものであるように感じる。
-移動は、暮らしの豊かさに直結する
ではここからは、おおかで行われている取り組み、いわば「川前版の健康おせっかい」を紹介していこう。
しばらく「桶売中学校、ありがとう」の看板の前で考え事をしていた私は、看板を後にし、ようやく「小さな拠点おおか」に到着した。拠点には、すでにたくさんの人が集まっていて、小雨が降っていることを感じさせない盛況ぶりだった。

ハレの日を迎えた、小さな拠点おおか
拠点の玄関には、ひと休みできるベンチと「Welcome おおか」と書かれたボード、そしてグランドオープンをお祝いするお花が飾られていた。受付を担当していた住民の方が、「このベンチは、もともと大工だったおとうさんがつくってくれて、手書きのボードは川前町の地域おこし協力隊の方が書いてくれたのよ」と教えてくれた。玄関からすでに川前づくしである。

細部にも「川前愛」が宿る
受付を終えて中に入ると、築70年の古民家が綺麗にリノベーションされた様子が目に飛び込んできた。まずは床。リノベーション前に取材した時は一面畳張だったが、冬でも寒さをしのげるように断熱材を入れ、カーペットも敷かれていた。広々と使えるよう、居間と廊下を仕切っていた障子は外されていた。
奥に並べられた机には、普段からおおかに通っているであろうおかあさんたちが集まって、おしゃべりをしていた。この日は、私のように取材にきた記者やテレビ局のカメラマンもたくさん集まっていたが、そうした状況でも楽しそうにおしゃべりを続けられるのは、おかあさんたちにとって、ここが日常だからかもしれない。

おかあさんたちにとっての「日常」
定刻になり最初に行われたのは、自家用有償旅客運送「おおか号」の出発式。自家用有償旅客運送は、バスやタクシーなど、十分な移動サービスが提供されない過疎地域などで住民の日常の移動手段を確保するために、行政やNPOが車両を提供して有償で運送する仕組みである。

おおか号の門出を祝うセレモニー
自家用車を用いた運送形態は、路線バスが廃止した場合の代替案として半世紀前から実践され、地域の移動のニーズに対して、NPO法人などの構成員が、交通空白地での交通事業を行える体制になっている。福島県のNPO法人では、おおかが2例目だ。
おおか号は、いわき市と特定非営利活動法人小さな拠点おおかの協働で運営されていて、車両の提供と運営資金の補助をいわき市が、運転手の確保と安定運用、利用促進のための情報発信をおおかが行うというパートナーシップ協定を結んでいる。つまり、おおか号の運転手を担うのは、おおかの登録ドライバーのみなさんということになる。
当日、おかあさん達を乗せてはじめての送迎が行われた。試乗したおかあさんはこんなことを語ってくれた。「運転免許を返納して自由に動けなくなって、自宅で泣いてしまうこともあったなあ。こんなにも気分が落ち込むなんて、びっくりした。でも、おおかに通うようになって少しずつ元気を取り戻している。送迎がはじまるのはありがたいのよ」。

地域のみなさんに見守られながらの出発

おおか号が、おおかまでの移動をサポートする
移動が、暮らしの豊かさに大きく関わっていることをひしひしと感じた。住民と行政とが協働で運営する自家用有償旅客運送は、中之作をはじめ、路線バスの廃止によって移動手段の確保が困難になった自治体の参考になる取り組みかもしれない。
-つくり手にまわれること
出発式に続いて行われたのは、コミュニティカフェ「小さな拠点おおか」のグランドオープン。いわき市長をはじめ、来賓で参加されていたみなさんに向けた試食会が行われた。この日のメニューは、おこわ、赤飯、てづくりのコロッケなどのおかず、野菜のスープ、からし菜のおひたし。デザートには、バナナロールケーキとコーヒーが出され、フルコースだった。

お手製の「おおか飯」
厨房に向かうと、5~6人のおかあさん達がせっせとランチの仕込みを行っていた。このおかあさん達は、ボランティアで調理を手伝っているという。「今朝、おおかに通うおかあさんが、畑で育てているからし菜を差し入れにもってきてくれたんですよ。せっかくだから、からし菜のおひたしも追加しようということで、急遽メニューに加えました」と裏話を教えてもらった。からし菜だけでなく、料理に使われる野菜とお米は、ほぼ地域の方からのもらいものなんだとか。
料理が得意な方は調理ボランティアで、農業を営む方は野菜の提供で。そんなふうに、なにかしらで貢献できる場所のほうが、だれかに助けてもらうばかりの場所よりも心地いい。コミュニティカフェのミソは、つくる人と食べる人、支える人と支えられる人とが時に逆転するところにあると感じた。

料理が「つくる」関わりしろに
「冷めないうちにはやぐ食べでって」と言われたため、厨房の見学を切り上げてテーブルに座る。同じ卓に座っていたのは、川前を離れ、現在はいわきの中心部で暮らすという息子さんご夫婦。さきほど食べてと声をかけてくださった方の息子さんだ。
春休みということで、小学校に通うお孫さんも連れていた。昔話に花を咲かせる息子さんとおかあさん達のやりとりを聞きながら、ランチプレートを食べ進める。採れたてのからし菜の辛味がツンと鼻にきた。川前で採れた野菜がたっぷり入った手づくりごはんがある限り、ここがふるさとに思いを寄せる人たちの居場所になり続けるのだろう。

手土産をもって、ふるさとに駆けつけた
-まちをケアする拠点
出発式と試食会がひと段落したところで、おおかの構想を立ちあげた川前町出身の比佐一枝さんと、昨年度まで小川・川前地域包括支援センターの管理者を務めていた藤館友紀さんに、おおかが歩んできた道のりをふり返っていただいた。
藤舘「今日、雰囲気を見て感じられたと思いますが、リノベーションもコミュニティカフェも、川前のみなさんに支えられながらやってきました。雨の日にお客さんが少なくなることを見越して、今日顔出しにいくねと事前に電話してくれる方もいます。」

藤舘さんは、セレモニーの司会を務めた
比佐「試行錯誤の日々でしたが、地元のみなさんとおおかをはじめてよかったと思います。地域留学プログラムの一環で都内の大学生が川前に訪れたり、山形県で地域に根ざした医療を行なっている医師の先生から問い合わせがあったりと、県外にも反響が広がりました。」

おおかを支える、川前町出身の比佐さん
藤舘「地域留学で大学生を受け入れたときは、地元のみなさんと一緒にプログラグラムを考えましたね。川前らしさを体験してもらうためのアイディアをすでにお持ちの方ばかりですからね。小さな企画を実現する機会にもなりました。」
一人ひとりの得意なことを形にしながら、おおかを拠点とした助け合うコミュニティを築いていく。藤館さんや比佐さんは、「人とつながり、まちを元気にする」コミュニティナースのあり方をまさに体現していると感じた。
さらに深く川前に根ざすために、藤館さんは隣町の小川町の薬局で働きながら、おおかの専任スタッフを務めるスタイルにチェンジしたという。小川町の薬局では、薬局がない川前町の課題をカバーするために、小川町の薬剤師と連携した体制づくりに取り組む。川前のみなさんの覚悟が、藤館さんの人生に大きな影響を与えたといっても過言ではない。
病院や学校がなくなり、あたりまえの生活を送るのさえ難しいと思われていた川前町にはいま、拠点を構えながら自分たちの手で暮らしをつくっている人たちがいる。今回出会ったみなさんがいきいきしていたのは、「最期まで住み慣れた川前で暮らすために、自分にできることをやりたい」という思いを実現しているからだろう。
さまざまなサービスがなくなっていく中で、自分の住みたい場所で暮らし続けることは簡単ではないが、思いさえあれば、思いに共感した仲間やアイディアが集まり、市民の手でサービスを担うことができるという事実を、川前のみなさんが示してくれた。
とはいえ、川前の取り組みをそのままそっくり取り入れればよいということではない。なぜなら、地域によっておかれている状況や地域資源は異なるからだ。身近な他者を気にかけるように、自分たちが暮らすまちの未来に関心をもつこと。みんなでまちをケアする視点が、行政や民間企業と市民との協働を生み出す鍵を握っているのかもしれない。
公開日:2025年01月01日